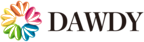初心者必見!おススメ空き地活用法5選!注意点も解説します
最近都市部や郊外でも、使い道がなく雑草が生い茂る空き地が増えています。また駐車場にするには狭い狭小地も増加しています。「何かに活用できないかな?」と思いつつも、実際にどんな方法があるのか分からず、そのまま放置してしまっている方も多いのではないでしょうか。しかも、空き地はただ管理するだけでは固定資産税がかかります。実は少し工夫するだけで、新たな不動産収入や地域貢献の場に変えることができるのです。
そこで本記事では、初心者の方でも簡単にできる空き地活用方法を10個ご紹介します。いずれも、実際の空き地活用実例を交えながら解説していきます。例えば人気の「駐車場経営」や「コインパーキング」だけでなく、注目の「レンタルスペース」や「移動販売拠点」など時代のニーズに合わせた方法もあります。
また空き地の活用方法は、広さや立地によって異なります。それは「自分の土地に合う活用方法はどれか?」を考える良いキッカケにもなるでしょう。初めて空き地活用を検討する方は是非参考にして下さい!
Contents
1. 初心者必見!空き地活用の基本
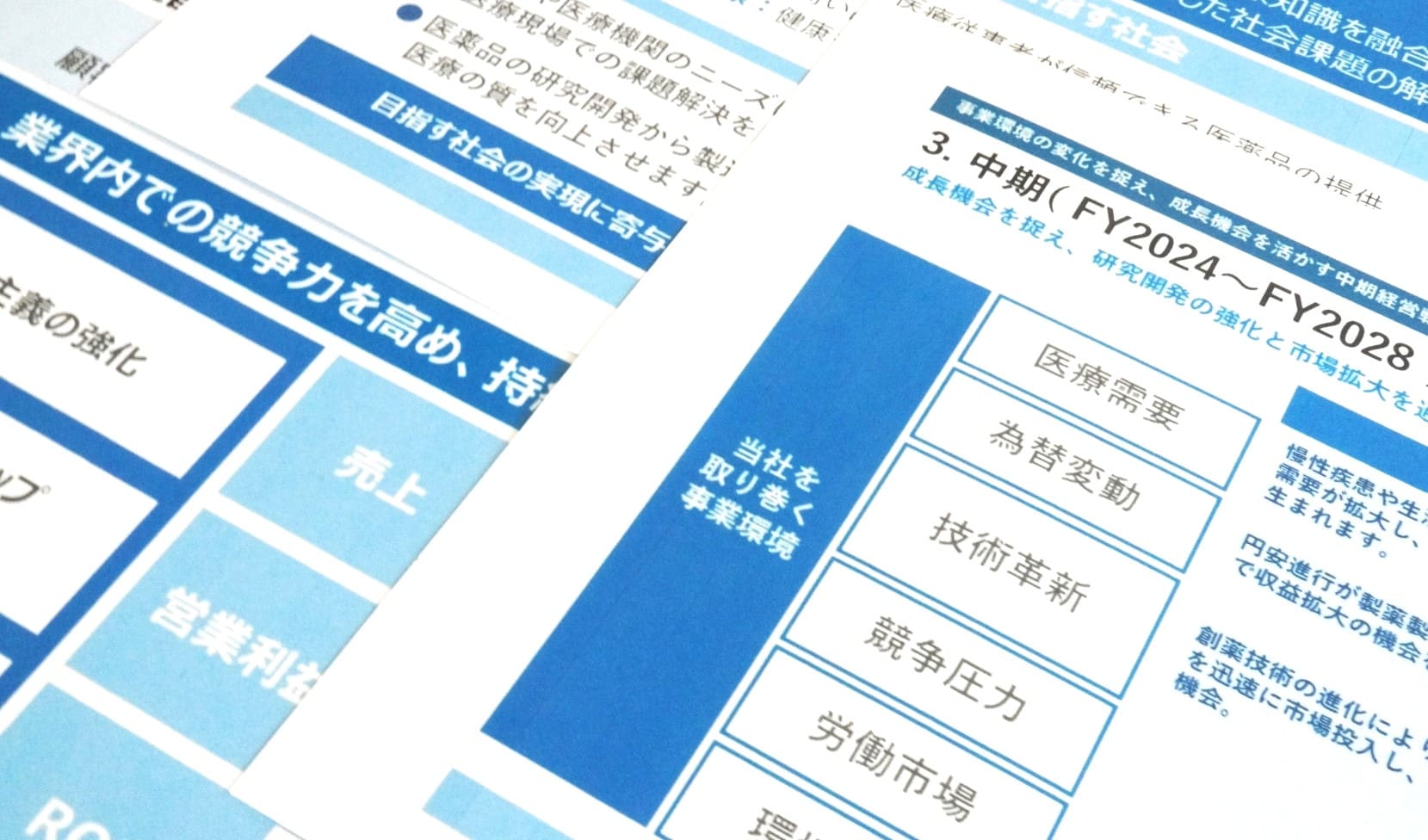
1-1. 空き地とは?その定義と種類
よく耳にする空き地とは、実際にはどのように定義されるのでしょうか。空き地とは、建物が建っていない土地や、利用目的が定まらず放置されている土地を指します。例えば東京の住宅街でも、相続後に使われず雑草が生い茂る空き地を目にすることがあります。雑草対策が不十分だと害虫の発生や景観の悪化につながり、近隣住民から苦情が寄せられるケースも少なくありません。また土地を所有している限り固定資産税は発生するため、何もせずに放置しておくことは所有者にとって大きな負担となります。
空き地にはいくつかの種類があります。例えば更地のままの土地、以前建物があり解体後に残された土地、そして空き家が取り壊されず残っている土地も空き地に含まれる場合があります。狸小路のような商店街エリアでは、空き地や空き店舗が地域活性化の課題になります。また地方では、空き家バンクを通じて賃貸や売買に結びつける取り組みが進められています。
1-2. 空き地を活用する目的とメリット
空き地を所有している方にとって活用する目的は、大きく分けて「収益化」と「土地の維持管理」の2つです。特に東京のような都市部では土地の価値が高いため、不動産投資として空き地を有効に使うことは非常に有利な選択肢となります。例えば駐車場として整備すれば、初期費用を抑えながら不動産収入を得られます。また自販機設置を組み合わせて、利用者の利便性と不労所得を得られる可能性もあります。
さらに、空き地を活用することで固定資産税の負担を実質的に軽減できる点も見逃せません。空き地は放置しているだけではコストがかかり続けますが、収益を生み出せば資産としての価値が一層高まります。中長期的に見ても、安定したキャッシュフローを確保できるのは大きなメリットです。副業感覚で始めて、最終的には不労所得に近い形で土地を活かせるのも魅力でしょう。つまり空き地活用は「余っている土地をお金に変える」だけでありません。土地を守り、将来の資産形成につなげる有効な手段なのです。
1-3. 空き地活用における注意点
空き地を活用する際には、収益性だけでなく、いくつかの重要な注意点を理解する必要があります。例えば駐車場経営や貸地といった方法でも、近隣住民とのトラブルの可能性があります。また騒音や不法投棄、車両の出入りによる安全面の懸念など、日常的なリスクを想定する必要があります。
また土地の権利関係も要注意です。借地権が付いた底地や再建築不可の土地は、活用方法が制限されます。さらに地目が宅地か農地かによって規制が変わります。例えば農地の場合は、農地法が適用され転用には許可が必要です。都市部では都市計画法や自治体の条例が関わるケースもあり、法令に違反すると思わぬ損失につながります。
空き地の活用は、経済的な側面でも慎重さが求められます。例えば収益を見込んで運用を始めても、初期投資や維持費が収入を上回れば意味がありません。そのため収支計画を作成し、数年先を見越したシミュレーションが成功のカギとなります。
2. 人気の空き地活用法7選
2-1. 賃貸マンション・アパートの運営

2-1-1. 賃貸マンション・アパートの収益性
空き地活用の中でも人気が高いのが、賃貸マンション・アパート経営です。その最大の魅力は、安定したキャッシュフローを生みやすい点にあります。ただし、その収益性を見極めるには複数の要素を考慮する必要があります。まず検討すべきは、建てやすさと投資額です。例えば軽量鉄骨造のアパートは比較的工事費が安く済み、短期間で運用を始められます。一方鉄筋コンクリート造のマンションは、耐用年数が長く資産価値も維持しやすいですが、初期投資が大きくなる点を押さえておきましょう。
運営面では、賃料下落リスクや空室リスクを考慮することが欠かせません。景気やエリア特性によって賃料が下がれば、当初想定していた収益を確保できなくなる場合があります。また運営中には維持管理費や定期的に必要となる大規模修繕費がかかり、長期的な収支に影響を与えます。これらの費用を踏まえた資金計画を立てることが、安定的な経営に直結します。
2-1-2. 建設の流れと注意点

賃貸マンション・アパート経営を始めるには、まず土地活用相談からスタートします。次に立地や需要を踏まえてプランを検討し、建物の間取りや仕様を決める設計に進みます。この段階では工法の選択も重要で、コストや耐用年数に直結します。次に建設会社を決定し、自己資金用意や融資の準備を経て、正式な契約締結へと進みます。着工前には地域慣習に応じて地鎮祭を行い、建物の骨組みが完成した時点で上棟式を執り行うケースもあります。
その後施工が進み竣工を迎えた段階で、初めて入居募集が可能になります。注意点としては、資金計画を綿密に立てること、建設会社との契約内容を十分に確認することが挙げられます。こうした手順を踏むことで、初めて安定した賃貸経営が実現できるのです。
2-2. 月極駐車場の運営

2-2-1. 月極駐車場の収益性

月極駐車場経営も、空き地活用で人気の高い手法です。その魅力は少ない予算で始められ、営業開始まで短い点にあります。例えば建物を建てる必要がありません。アスファルト舗装や区画線を引けば、すぐに開始できます。しかも狭い土地や変形した土地でも、運用できる柔軟性があります。特に都市部のように車の需要が高いエリアでは、「儲かる場所なら儲かる」ビジネスモデルといえます。
収益性では、他の不動産投資に比べて安定感があります。マンション経営のように、空室リスクに大きく左右されることはありません。ただし契約・解約業務をオーナーが直接行う場合は手間がかかるため、管理委託を利用するケースも多いです。実際の利回りは一般的には実質利回り4%前後とされ、堅実な投資対象として評価されています。また税制面でのメリットも見逃せません。駐車場の多くは雑種地として扱われます。そのため建物より固定資産税や都市計画税が安く済む場合があります。
2-2-2. 設置の流れと注意点
月極駐車場の安定した運営には、正しい準備と注意が欠かせません。まずは事業計画を立て、収益と費用の試算を行うことが第一歩です。次に需要を見極めるための土地の調査と選定を行い、区画数や動線を考慮したレイアウト設計に進みます。設備としては、利用形態によって精算機やゲートを設置する場合もあり、時間貸し駐車場との違いを意識して検討することが重要です。また開業前には、行政への届け出や税金や保険の確認を済ませる必要があります。工事が完了した後は、需要に応じた料金設定を行い、契約後のトラブル対応の体制を整えておくことも忘れてはいけません。これらを踏まえることで、初めて安心して運営できる駐車場が完成します。
2-3. トランクルームの運営

2-3-1. トランクルームの需要と利点

空き地や空室を活用する方法の一つとして注目を集めているのが、トランクルーム投資です。実際近年のトランクルーム市場は上昇傾向にあり、全国的に利用者数が増加しています。特に都市部では住宅の収納スペースが不足していることから需要が高まり、東京や横浜といったエリアを中心に拡大が続いています。中でも新宿周辺の事例では、オフィスワーカーや単身世帯からのニーズが強く、相場は月額数千円から数万円と幅広い価格帯で取引されています。
トランクルームには、大きく分けて屋外型と屋内型があります。屋外型はコンテナを設置して比較的低コストで始められるのが特徴で、土地活用の入門として人気です。一方屋内型は空きビルやマンションの一角を利用するスタイルで、セキュリティ面が強化されているため、法人利用や長期契約につながりやすい利点があります。しかも駐車場や賃貸経営と比較して、初期費用を抑えやすいのも魅力です。
2-3-2. 管理と運営における注意点
トランクルーム経営は安定収益を期待できる不動産投資ですが、成功のカギは運営体制にあります。特に重要なのが、管理会社選定です。提供されるサービス内容や料金だけでなく、評判と過去の実績を確認することが欠かせません。特に利用者からの問い合わせやトラブル対応を迅速に行えるかどうかは、大事です。また地域特性を理解しているかどうかもポイントです。地域密着性の高い管理会社であれば、需要動向を把握し、柔軟な運営が期待できます。さらにオーナーが不利益を被らないように、契約内容を十分に確認しておくことも大切です。安易に契約せず、複数社を比較検討することでリスクを抑え、安定した運営が実現できます。
2-4. 自動販売機設置

2-4-1. 選定する商品と場所のポイント

自動販売機
自動販売機設置を検討する際には、まず選定する商品が、大きなポイントとなります。飲料を中心にするのか、スナック菓子や日用品を扱うのかによって、ターゲット層や売上の見込みが変わります。次に考えるべきは、場所です。人通りの多いオフィス街や学校近く、あるいは住宅地の一角など、需要が見込める場所を選ぶことで、安定した収入につながります。設置による収益は本数や単価によって左右されますが、場所と商品選定を工夫すれば副収入として十分魅力的です。
一方で、導入費用も見逃せません。自動販売機本体のリース代や購入費、補充やメンテナンスにかかる経費が必要です。また常に稼働させるためは、電気代も発生します。近年は省エネ型の機種が普及しており、従来よりも電気代を抑えられるケースも増えています。さらに最近では売上や在庫をスマホで確認できるアプリと連動した機種もあり、効率的な運営が可能です。
2-4-2. 収益と管理の手間について
自動販売機設置は、人通りの多い場所に設置できれば、飲料や軽食などの商品は日々自動的に売れます。その結果、労力をかけずに売上が積み上がります。さらに設置場所によっては、メーカー本体や商品補充を行う契約もあります。一方自主管理する場合、仕入れや補充、売上金の回収、在庫管理を行う必要があります。また夏場には冷却機能を常に稼働させるための電気代も発生し、これは収益を圧迫する要因になり得ます。また設置の際には初期費用として本体の購入やリース代がかかります。
2-5. 電動キックボードの設置

2-5-1. 初期費用も維持費も不要

近年、都市部を中心にシェア型の電動キックボードが急速に普及しています。これを自宅や店舗、宿泊施設に導入する「電動キックボード設置」は、新たな集客や利便性向上の手段として注目されています。大きな魅力の一つは、初期費用0円で始められるプランが多い点です。設置自体は事業者が行い、オーナー側が高額な購入資金を負担する必要はありません。さらに維持費不要で、メンテナンスやバッテリー交換といった管理業務も運営会社が対応するため、オーナーの手間はほとんどかかりません。
導入のメリットは収益性だけではなく、物件や店舗の価値向上にもつながります。例えば賃貸住宅に導入すれば、賃貸マンション入居者増加効果が期待できます。入居者は移動手段が確保されている安心感を得られるため、競合物件との差別化につながるのです。また商業エリアでは、飲食店集客効果が見込めます。来店手段として手軽に利用できるため、来客数アップに直結します。
2-5-2. 地球に優しいエコな引移動手段としても注目
近年注目を集める電動キックボードは、環境負荷を抑えた新しいモビリティとして人気が高まっています。従来の自動車やバイクと比較すると、CO2排出量が圧倒的に少ないのは大きなメリットです。将来的に持続可能な社会に向けた移動手段として期待されています。電動キックボードはガソリンを使わず、電気で駆動します。そのため大気汚染や騒音の軽減にもつながり、都市部での利用に最適です。また近年では立ち乗りタイプだけでなく着席型も登場しています。着席型は、長距離移動や高齢者にも利用しやすいというメリットがあります。

渋谷のLimeの設置ポート例。店前の狭い場所でも活用でき集客効果も
3. リスクヘッジのための事業併用

都市部や郊外において、空き地の有効活用はオーナーにとって重要なテーマです。特に最近注目されているのが、複数の活用法の組み合わせによる事業展開です。例えば単独で駐車場経営を行う場合、需要の変動によって収益が安定しないリスクがあります。しかし駐車場と他のサービスを併せて運営することでリスクヘッジとなり、長期的に安定した収入を確保しやすくなります。
その代表例が、駐車場と電動キックボードの併用です。車を利用する人には駐車スペースを提供しつつ、近距離移動や観光目的の利用者には電動キックボードを貸し出すことで、幅広いニーズに対応できます。これにより収益源が多様化し、空き地の収益性が一層高まります。しかも電動キックボードは環境に優しい移動手段として注目されています。そのため地域のイメージ向上にも寄与する点も魅力です。
4. まとめ
空き地を有効に活用する方法は数多くあります。そして収益を安定的に確保するためには、成功ポイントを押さえることが重要です。まず第一に、利用者にとって良いサービスを提供できるかどうかが大きな鍵となります。例えば駐車場なら利便性や料金設定、電動キックボードやシェアサービスなら使いやすさや安全性が重要です。土地活用は単にスペースを貸すだけでなく、利用者の満足度を高める工夫によって継続的な収入につながります。
次に大切なのが、優良事業主の選定です。オーナーがすべてを自主管理するのは大きな負担となるため、実績があり信頼できる事業者に運営を任せることで安定性が増します。パートナー選びを誤ると、収益が不安定になったりトラブルが発生する可能性があります。そのため、契約内容やサポート体制を十分に確認することが欠かせません。さらに精緻な収支計画も重要です。例えば初期投資や維持費用を把握し、リスクを最小限に抑えます。
◆<空いてるスペースを収入に変えませんか>◆
近年、街中でよく見かける電動キックボード。その設置場所を提供するだけで、毎月固定の収入が入ってきます。賃料の価格は場所で変わります。金額の目安は1台あたり1,500円~5,000円です。仮に1台2,500円で4台置ければ、毎月1万円の収入になります。しかも設置費用や維持費は一切かかりません。少しでもご興味があれば、まずはお気軽にこちらのページ下のコンタクトフォームからお問い合わせ下さい。